こんにちは!ときどき校長です。
一般的には行事の多い2学期ですが、その行事の中でさまざまなドラマが生まれ、行事を節目にして子どもたちは大きく成長していくことがあります。運動会に向けてがんばっている先生方もたくさんおられることでしょう。今日は運動会について…
私がロサンゼルス補習授業校に派遣勤務していたときのことです。そこで行われた運動会は、子どもも親もみんなが楽しみにしている一大イベントでした。(補習校ですから、日々の授業には体育はありません。一年に一度だけ秋に運動会があるのです。)中には「運動会があるから補習授業校に通っている」という子もいて、その期待の大きさを肌で感じました。
日本では当たり前にある運動会ですが、アメリカの現地校ではなかなか経験できません。だからこそ、保護者にとっては「懐かしい日本の文化」を味わえる場になり、子どもたちにとっては「日本の学校文化を体験できる特別な時間」となっていました。改めて、運動会には単なる競技以上の文化的・教育的な意味があると強く感じた瞬間でもありました。
1. 努力のプロセスを体感する
〜小さな挑戦も、大きな成長〜
運動会の価値は、勝敗や順位だけではありません。練習を重ねる中で、子どもは「昨日できなかったことが少しずつできるようになる」という体験を積み重ねます。教師として大切なのは、その努力の過程をきちんと認めてあげることです。
例えば徒競走で、速く走れなくても最後まで全力で走り切ること。それ自体が大きな成長です。「順位」ではなく「挑戦した姿勢」や「積み重ねた努力」を言葉で伝えることがポイントです。
2. 協力と役割意識を育む
〜チームの中の自分の存在に気づく〜
団体競技や表現種目は、仲間と力を合わせることの大切さを学ぶ絶好の場です。一人の頑張りだけでなく、全体の中でどう動き、どんな役割を担うかが問われます。
ここで教師として大切にしたいのは、「一人ひとりが欠かせない存在だ」ということを伝えることです。目立つ役割も、裏方や支える役割も同じくらい価値があります。それを言葉や態度で示すことが指導のポイントです。
私がロサンゼルスで経験した運動会で、こんなことがありました。中学部3年の男の子に「運動会どうだった?」と聞くと、彼は「めちゃくちゃよかったです。」と答えました。彼は応援団長であり、放送係でもありましたが、チームは残念ながら勝てませんでした。「チームとしては残念ながら負けちゃったね。それでも良かったんだ。」と言うと、彼は、「放送係として盛り上げることができたし、運動会の成功に貢献できた。」と誇らしげに話してくれました。勝敗にとらわれず、自分の役割で全体に貢献できたことの喜びを感じている姿に、私は胸を打たれました。
3. 成功も失敗も学びに変える
〜失敗は、次の成長へのステップ〜
運動会では、勝つ喜びもあれば負ける悔しさもあります。転んでしまった子、バトンを落とした子…。それでも最後までやり切った経験には、大きな学びがあります。
教師として大切なのは、結果よりも「そこに至る努力」と「最後までやり切ったこと」を肯定的に受け止めることです。どこにフォーカスするかということが大切です。「転んでも立ち上がった勇気」や「仲間を思った気持ち」を拾い上げてあげることで、子どもの自己肯定感は育ちます。
4. 感情を育てる舞台
〜泣いても笑っても、学びの一部〜
運動会は、普段の授業では味わえない感情を経験できる舞台です。緊張やドキドキ、嬉しさや悔しさ…。
教師ができることは、こうした感情を受け止め、整理の手助けをすることです。泣くことも笑うことも、すべて学びの一部だと伝え、仲間と気持ちを共有できる場を作ることが大切です。
5. 教育観の変化を映す鏡
〜子どもたちに合った運動会の形を考える〜
近年、運動会は大きく変わってきています。以前は「規律」や「集団美」が重視されましたが、今は「安全」「多様性」「個々の成長」に教育の軸が移っています。組体操の縮小や順位の見直しを行う学校も増えています。
教師として大切なのは、伝統を大切にしつつも、今の子どもたちに意味のある運動会をどう作るかを考えることです。子どもたちの安全と学びを第一に考える柔軟な姿勢が求められます。
6. 教師としての指導のヒント
- 努力を言葉で認める:「最後まで頑張ったね」「昨日より速く走れたね」
- 全員の存在を価値づける:前に出る子も、裏方の子も同じくらいに称賛する
- 失敗を前向きに捉える:「転んでも立ち上がった勇気が素晴らしい」
- 感情を受け止める:泣いてもいい、悔しがってもいい、その気持ちを共有する
- 教育観の変化に敏感でいる:子どもたちの時代に合った指導を意識する
おわりに
〜運動会は人生の原体験になる〜
運動会は、子どもにとって大きな挑戦の場であり、教師にとっては教育の力を試される場でもあります。大切なのは、子ども一人ひとりが「やってよかった」「自分は成長できた」と感じられる経験を支えることです。
その際、大切なのは運動会の当日だけでなく、計画段階から子どもたちに参加をさせるということです。自分たちで考え、自分たちで計画し、自分たちでやり切り、自分たちで振り返る。学習にしろ、行事にしろ、このプロセスを大切にすることこそが子どもたちに、生きる力を育てていくことになると思います。
教師が子どもたちの努力や協力を丁寧に認め、失敗も成長の糧として価値づけるとき、運動会は単なる学校行事ではなく、人生を支える「学びの原体験」となります。どうぞ実りのある運動会になりますように。


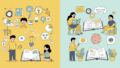
コメント