子どもたちと「幸せ」を育むヒント|教師のための幸福学
皆さん、こんにちは。ときどき校長です。
多忙な2学期が本格的にスタートし、先生方は授業準備や行事の計画で、あっという間に時間が過ぎていくことと思います。しかし、この多忙な時期だからこそ、子どもたちと向き合う時間、そして私たち自身が「幸せ」を感じられる時間を大切にしてほしいと願っています。
昨日、親向けに「幸福学」について紹介しましたが、これはもちろん学校、先生たちにとっても大切な観点ですので、今日は先生の視点からの「幸福学」を紹介したいと思います。日々の教室運営や授業にすぐに活かせる、シンプルで本質的な考え方です。
脳科学が示す「幸せの4つの因子」を教室に
「幸福学」は、脳内のドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質の働きや、数万人規模のアンケート調査に基づいています。慶應義塾大学の前野隆司先生が提唱する「幸せの4つの因子」は、子どもの自己肯定感を高め、学級をより良い方向へ導くための確かなヒントになります。
1. 「やってみよう!」因子(自己実現と成長)
- 実践のヒント: 子どもに「やってみたい」と思わせる授業を意識しましょう。先生が全てを教え込むのではなく、子どもたちの好奇心をくすぐる問いかけや、自由に探求できる時間を設けることが大切です。また、教えあいや学びあいの時間を作るというのも大切です。
- 具体例:
- 教えあいタイム:先生対子どものやりとりばかりにならないように、友だち同士の教えあいや学びあいをとります。ちょっと停滞したときに1分間。とか、隣の人じゃなくて出席の前後の子と相談等、様々なバージョンで教えあいタイムができるといいですね。
- 「正解のない問い」を投げかける:授業の終わり等に、「もしタイムマシンがあったら、過去に行って何を変えたい?」や「もし魔法が使えたら、どんな世界をつくりたい?」といった、正解が一つではない問いを投げかけます。子どもたちは、自分の考えを自由に発言することで、思考力や表現力を伸ばすだけでなく、先生が自分の個性を受け入れてくれるという安心感を得られます。
2. 「ありがとう!」因子(つながりと感謝)
- 実践のヒント: 教室を「ありがとう」があふれる温かい場所にしましょう。先生が率先して感謝を伝えるだけでなく、子ども同士が感謝を伝え合う機会を意図的に作ることが重要です。
- 具体例:
- 「ありがとうカード」を回す:週に一度、クラス全員で「〇〇さんに感謝したいこと」を書いて、カードを交換し合います。
- 役割を可視化する:係活動や当番活動など、見落とされがちな小さな役割にも感謝の言葉をかけることで、「自分はみんなの役に立っている」という実感が得られます。
3. 「なんとかなる!」因子(楽観性と強さ)
- 実践のヒント: 子どもが失敗や挫折を経験した時こそ、先生の出番です。「なんとかなる」という心の強さ(レジリエンス)を育てる指導を心がけましょう。
- 具体例:
- 「失敗ノート」をクラスで共有する: 子どもたちに、自分が頑張ったけれど失敗してしまった経験や、うまくいかなかったことをノートに書いてもらいます。先生も自身の失敗談を書き、定期的にクラスで発表し合います。
- 「再挑戦カード」をつくる: テストや発表、課題などで良い結果が出せなかった時に、子どもが「もう一度頑張りたい」と思ったら「再挑戦カード」を先生に提出するルールをつくります。
- 「解決策ブレインストーミング」を行う: クラスで何か問題が起きた時や、誰かが困っている時に、「どうすれば解決できるか」をみんなで自由にアイデアを出し合う時間を設けます。一つの問題に対して様々な解決策があることを知ることで、子どもたちの視野が広がり、「一人で抱え込まなくても大丈夫」「みんなで力を合わせればなんとかなる」という実感を育みます。
4. 「ありのままに!」因子(独立と自己肯定)
- 実践のヒント: 子どもたちを他者と比較しない指導を心がけましょう。一人ひとりの個性や「その子らしさ」を認め、尊重する言動は、子どもたちの自己肯定感を育てます。
- 具体例:
- 「いいね!ポイント」を探す:個人の提出物や発表に対して、「〇〇さんの、そういう考え方、面白いね」「この部分の工夫、先生は好きだな」など、具体的な「良い点」を見つけて伝えます。
- 「私だけの〇〇」を共有する:月に一度、「私だけの得意なこと」「私だけの好きなもの」を発表する時間を設けるなど、自分らしくいられる安心感を与えましょう。
まとめ:幸せの種をまく「教師」という仕事
「幸せ」は、特別な才能や環境がなくても、日々の関わりの中で育むことができるものです。
「やってみよう」「ありがとう」「なんとかなる」「ありのままに」
これらの4つの言葉と実践を、ぜひ先生自身の指導の「魔法の言葉」にしてみてください。子どもたちの心に幸せの種をまき、その成長を間近で見られることは、教師という仕事の最大の喜びだと信じています。


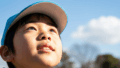
コメント